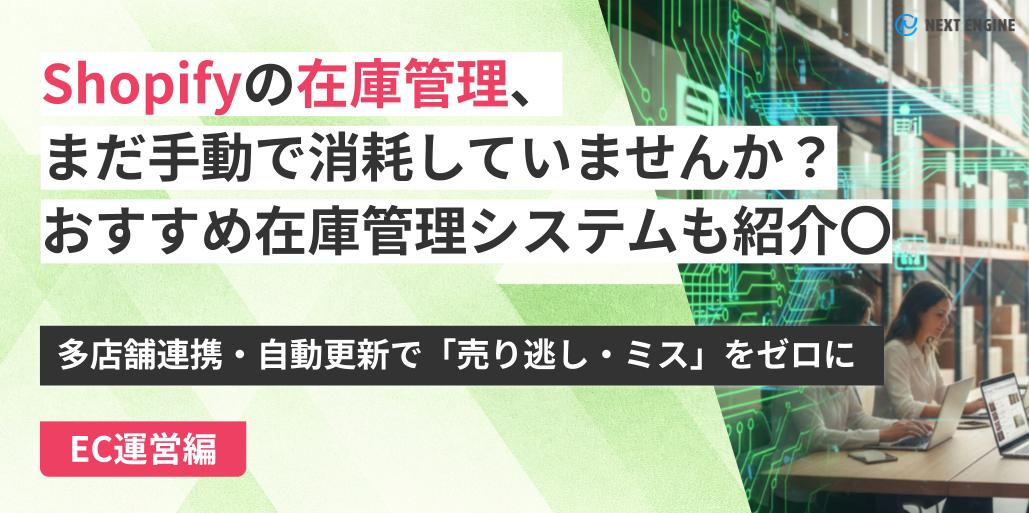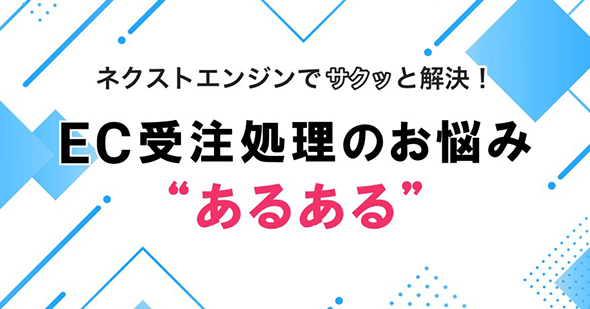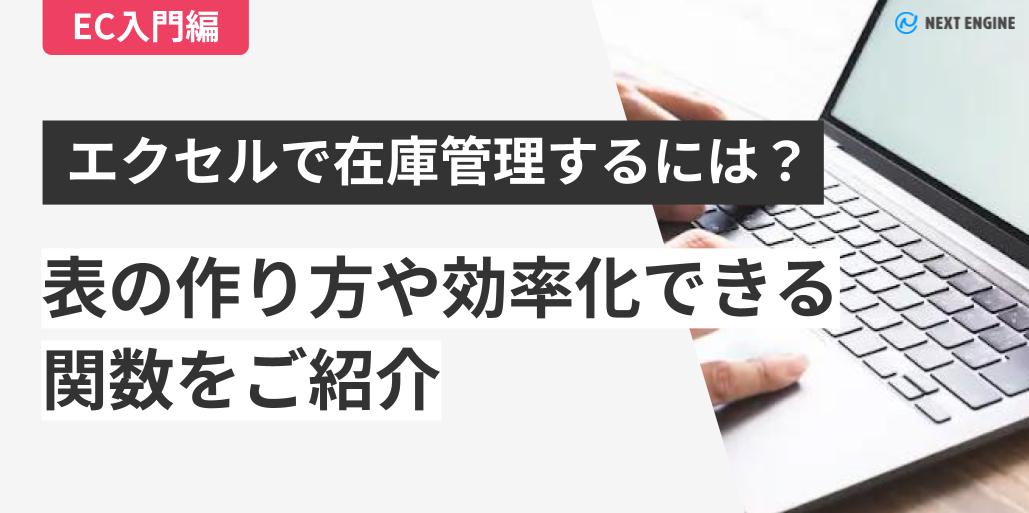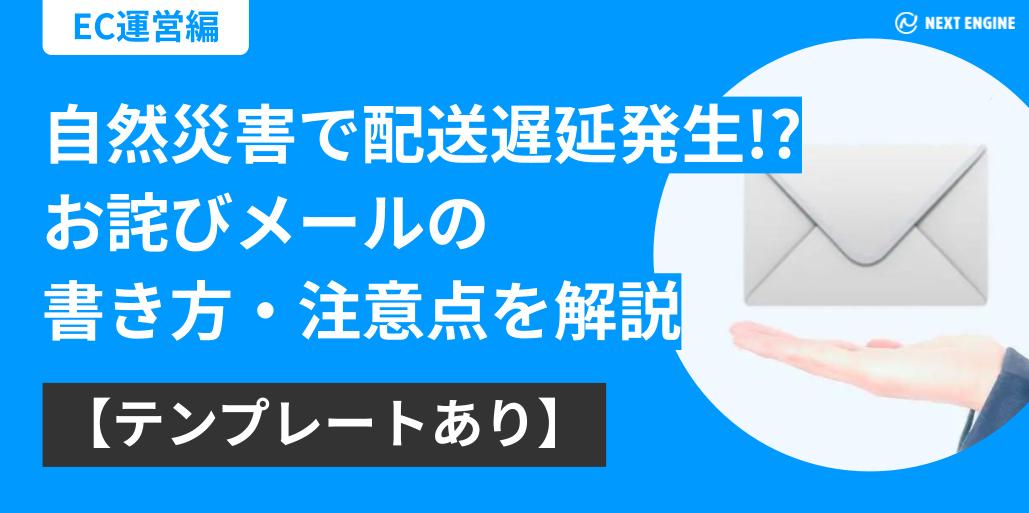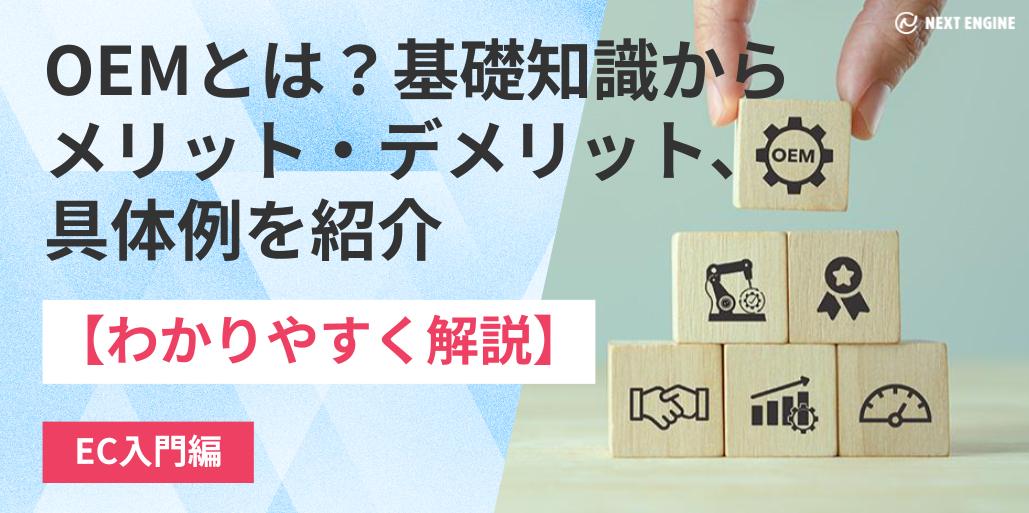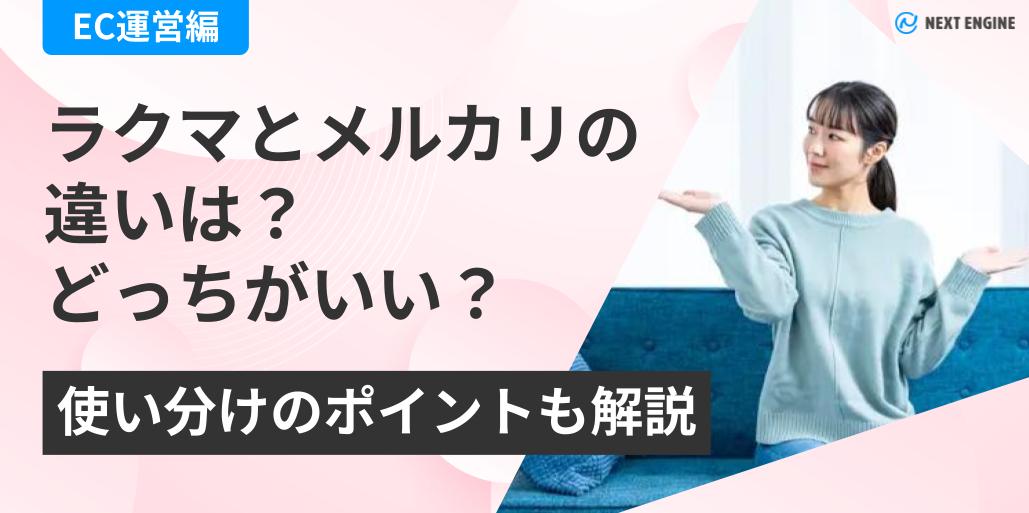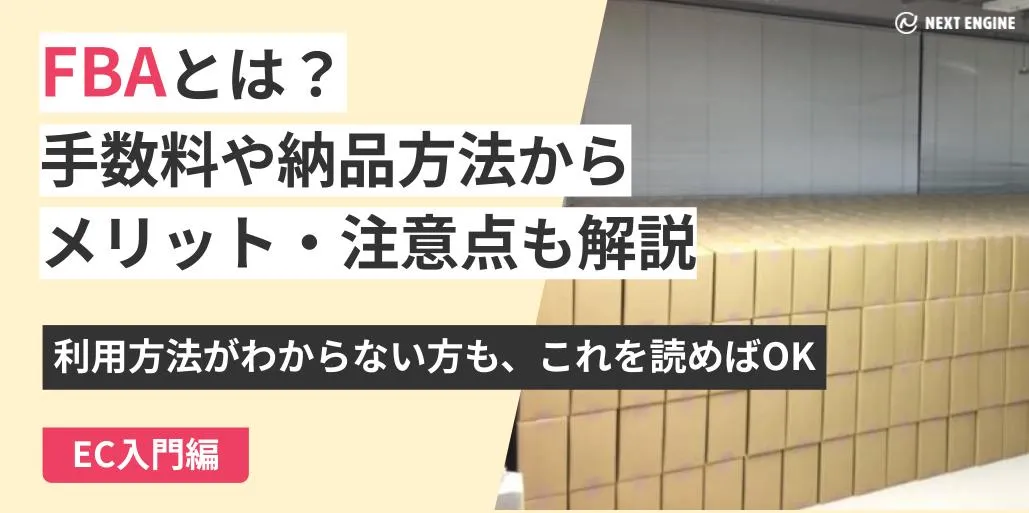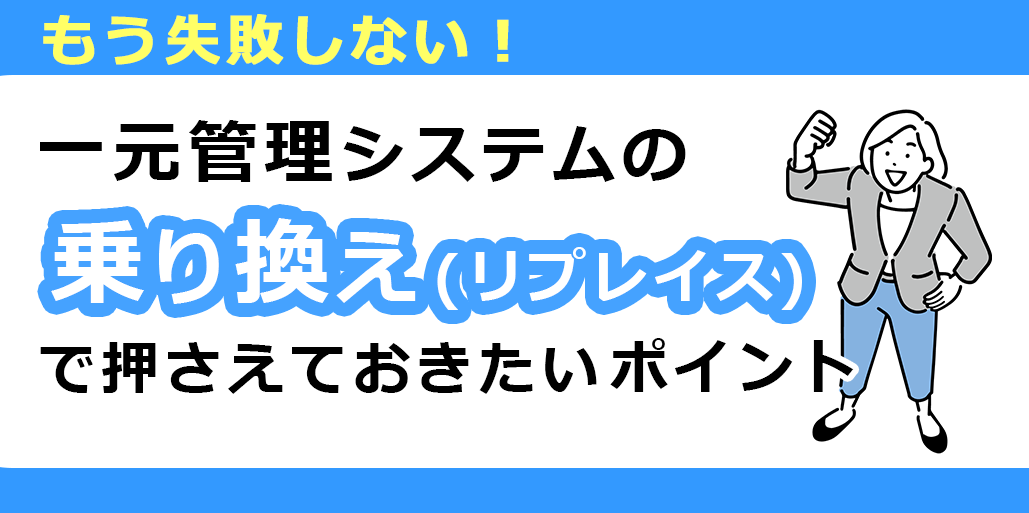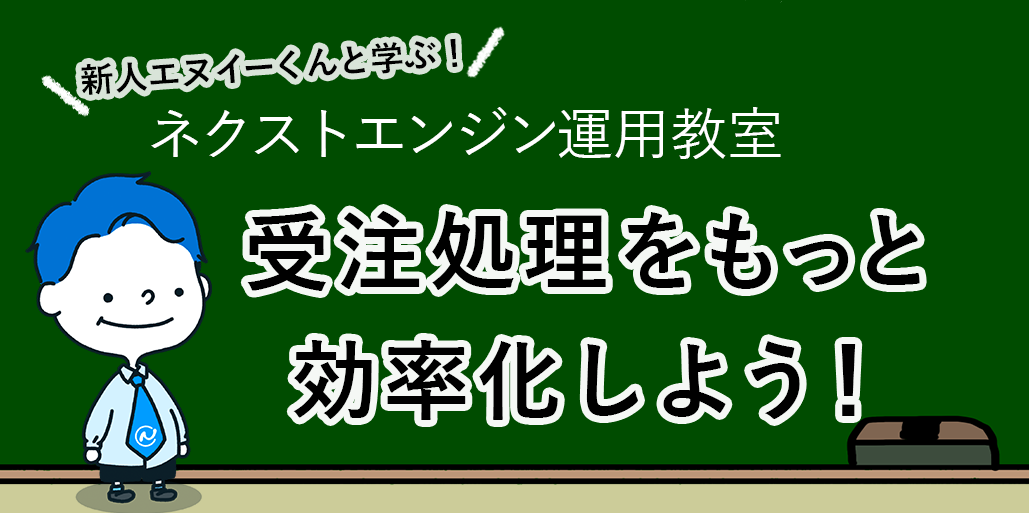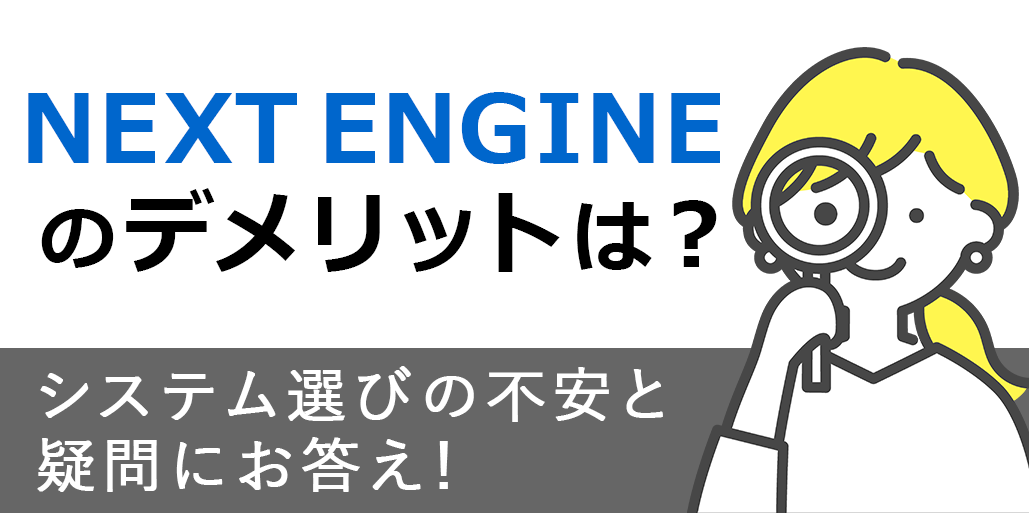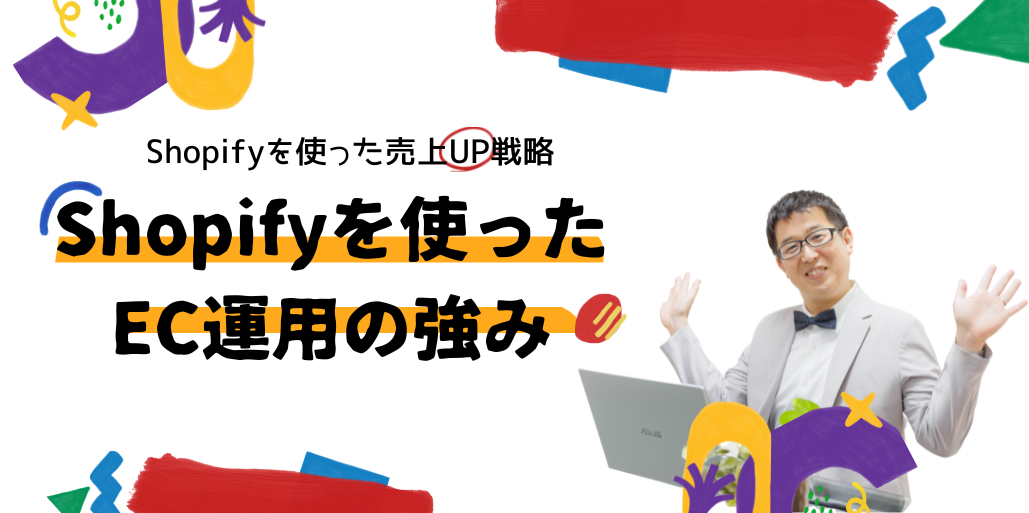
この記事では、Shopifyを使ったEC運用の強みについて紹介します。記事の内容は、15年間にわたってECサイトに関わり、いまではECサイトの運営サポートを手掛けている株式会社アプロ総研代表取締役の李重雄氏による講演※に基づいて構成しています(本記事内の話し手はアプロ総研の李氏)。同セミナーの「Shopify最新情報とEC運営体制について」はコチラ。
※2022年11月2日(水)開催のEC Growth Day「Shopifyを使った売上UP戦略とオペレーション構築の重要性」を動画でご覧になりたい方はアーカイブにてご視聴ください。
Shopifyの5つの強み
ECサイト運営向けにさまざまなプラットフォームが登場していますが、Shopifyを活用することで得られる5つの強みがあります。それぞれを紹介しましょう。
【強み1】サーバーが強固
Shopifyのサーバーは365日24時間体制で監視されていて、稼働率99.8%を誇るほど、安定性に定評があります。ネットショッピングでは、売上のチャンスは思いがけないタイミングでやってきます。芸能人やインフルエンサーの目に留まってSNSで紹介されたことがきっかけで商品に注目が集まり、一夜にして500万の売上があがるような事例もあるほどです。
しかし、商品が話題になっているときは、絶好の販売チャンスである反面、アクセスが集中するためにサーバーダウンの危険性が高まります。サイトにつながらない状態が発生してしまったら、大きなチャンスを逃してしまうことになります。
管理画面の操作性にもたつきを感じることはありますが、この点は改善が期待できます。それよりも、どれほどアクセスが集中してもサーバーダウンを心配する必要がないことは、サイト運営者にとっての大きな安心感につながり、サイトの信頼性を向上させます。
【強み2】充実したアプリ
Shopifyは、標準機能を拡張できるアプリが充実しています。
アプリストアには7,000以上のアプリが提供されているので、必要に応じて追加してカスタマイズすることで自社サイトの利便性を高められます。自分にとって必要なアプリが選びやすいように、アプリストアではカテゴリ別に検索できたり、おすすめのアプリや日本向けに用意されたアプリがまとめて紹介されています。
これだけの数のアプリが提供されているのは、おそらくアプリ提供業者に対するサポートが充実しているからでしょう。
アプリ提供事業者にとっても、アプリ利用者にとっても、望ましい環境が整えられているので、今後も良質なアプリのラインナップが増えていくだろうと予想されます。
ただし、残念ながらアプリの組み合わせの相性が悪い場合もあります。Shopify側で対策を講じているようですが、中には対応が間に合っていないものが存在することも事実です。
また、どれほどニッチなニーズでもアプリがあれば完璧にカバーできるかと言えば、まだそこまでは至っていません。EC運営に関して「こんなことがしたい」と思うことは、ほとんど支障なく解決できるでしょうが、利用者側で工夫する必要がある場合も散見されます。
これらの課題はニーズが高くなれば、対応するアプリが開発されて解決されるでしょうから、今後のさらなる拡充を期待していいと思います。
【強み3】ノーコードで運用可能
コードの知識がなくても日常のEC運用をこなせるのが、Shopifyの大きな強みです。
Shopifyには、自分自身でサイトデザインやテーマをカスタマイズできるように、テンプレート言語「Liquid(リキッド)」が用意されています。Shopifyのシェアが拡大するにつれ、Liquidが注目され、使い方を解説する情報なども見かけるようになってきました。
しかし、Liquidの使いこなしは必須事項ではありません。むしろ、アプロ総研で提供しているShopify初心者向けの支援サービスでは、最初のうちはLiquidを使わないことを推奨しているほどです。コードや仕組みを理解しないまま、不用意にLiquidに手を出してしまうと、思わぬ影響が出てしまうことがあるからです。
もちろん、コードを理解して正しく活用できる人、プログラム技術のある人は積極的にLiquidを活用するといいでしょう。よりオリジナル色を強めることができます。
しかし、敷居が高いのであれば、ノーコードでもShopifyは十分EC運用が可能です。
【強み4】ネクストエンジンとの連携
ECサイトを滞りなく運営するには、商品が売れた後に発生する事務処理、つまりバックオフィス処理を効率良く行うことが重要です。
近頃は、OMS(Order Management System/オーダーマネジメントシステム)やWMS(Warehouse Management System/倉庫管理システム)と呼ばれる、EC向けの一元管理システムが数々登場していて、これらを使っている人も多いと思います。
Shopifyには、マーケティング戦略などフロント業務に関わる機能は充実していますが、バックオフィス処理に関してはOMSやWMSにかないません。この点をカバーするためにShopifyではOMSやWMSとの連携機能を強化しています。
とくに、OMSの中でも定評のあるネクストエンジンはShopifyとの連携に力を入れていて、注文情報の自動取り込みや、配送キャリアの仕様に合わせた送り状の作成、メールの自動送信など、受注から在庫管理、出荷管理までの作業を自動化できます。バックオフィス処理を大きく効率化できます。
【強み5】エンタープライズ向け上位プランの優位性
扱う商品点数が増えたり売上規模が拡大するにつれ、新たな出店を計画したり、プラットフォームを見直してさらなる飛躍を図ろうとすることもあるでしょう。
しかし、新たなストアを開設しようとしたり、カートを変更しようとする際に、悩ましい課題になるのがデータの移行です。顧客情報という個人情報を扱うこともあり、慎重にデータを移行した結果、半年程度の期間を費やしたという事例もあるほどです。
この期間も成長できるはずだと考えると、データ移行だけで半年もの時間がとられるのは、無駄な足踏みにしかなりません。
Shopifyには、最上位のエンタープライズプランとして、Shopify PLUSが用意されています。Shopify PLUSには、追加料金なしでストアの数を増やしたり、既存ストアからのデータインポートなどの独自機能が用意されています。
成長に合わせて最適なプランを選べる余地があること、プランを変更するだけで圧倒的なスピード感で規模を拡大できることを考えると、Shopifyでの運用は自社ECの成長を加速したい人にとって大きな後押しになるでしょう。
Shopify運用で心がけたいこと3つ
強みとは逆に、ShopifyでのEC運用にあたって心がけておきたい注意点もあります。
【注意1】クラウドサービスであることを理解する
Shopifyは優れたサービスですが、多くの利用者に向けたクラウドサービスであるため、汎用性を意識した仕様になっているところもあります。
あつらえたようなフィット感を望むなら物足りなさを感じるかもしれませんが、オーダーメイドシステムでない以上、既製品に自分を合わせていく意識を持つことは必要です。
【注意2】新しいことに挑戦する
工夫のしがいがあるプラットフォームなので、無難で保守的な運用をするよりも、新たな挑戦をして大きな成長を目指していくことをおすすめします。
【注意3】顧客目線を忘れない
ECサイト運用していくにあたって最も重要なのは、やはりお客様の気持ちです。自分が何をしたいかよりも、購入者は何を望むのか、買いたいと思ってもらうには何をすべきかを考えた運用を心がけるようにすることが大切です。
――講演の内容をさらに詳しくご覧になりたい方は、アーカイブ視聴をご利用ください。
【講演者】

李 重雄
株式会社アプロ総研 代表取締役
大阪生まれ、大阪育ち。近畿大学理工学部経営工学科卒業後、株式会社ソフトウエア・サイエンスにSEとして入社。百貨店の顧客管理システム、スーパーのPOSシステム、自動車事故のコールセンターシステムなどを経験した後、2007年に大学時代の同級生と株式会社アルクムを設立。Movable TypeのプラグインとしてECパッケージ「AlTrade」を開発。2012年に株式会社アプロ総研を設立。